※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
Amazonプライム会員であれば、無料で本書を読めます(2025/7/26現在)。
Amazonプライム会員は30日間の無料体験ができます(初回登録のみ)。
Amazonプライム無料体験の新規登録Kindle Unlimitedに加入しても読めますよ。初回登録者は30日間無料で体験できます。
Kindle Unlimited 無料体験の新規登録この本を読んでほしい人
以下のような方におすすめの一冊です。
- 起業に興味がある人
- フリーランスや副業をしているが、なかなか軌道に乗らないと感じている人
- 自由でストレスの少ない働き方を目指したい人
「ひとりビジネス」とは、個人でお金を稼ぐことです。アルバイトやサラリーマンなどの雇用されて給与所得をもらうのではなく、副業などで事業所得を得ることです。
会社員としての人間関係や、やりたくない業務に悩んでいる人にとって、「ひとりビジネス」という選択肢はとても魅力的です。
ですが、自由な分だけ不安もあるのが現実。この本は、そんな人に「これならできる」と思わせてくれる一冊です。
本の内容
「ひとりビジネス」の自由さ
序章では、「やりたい仕事が変わっても大丈夫」「人間関係に縛られない」という、ひとりビジネスの自由さが強調されます。
「人間関係に縛られない」というのは、非常に大事だと痛感しています。私自身、上司との馬が合わずに苦戦しています。
自分で考えて行動しろと言われ、「このように取り組もうと考えています。」と伝えると、「○○する必要はあるの?」「○○しないのはなんで?」「その考えは論理的じゃないよね」と言われてしまいます。
上司の言っていること自体は間違っていないので、そこは納得できますが、伝え方はかなりトゲトゲしいため、私はその言葉に落ち込んでしまいます。
会社にいる以上、その人と顔を合わせることは避けられません。一方で、「ひとりビジネス」であれば、苦手な人とは仕事をしないという選択肢もあるため、人間関係における悩みを抱えにくいというメリットはあるかと思います(まったく悩まないというわけではないかと思いますが、、)。

「〇〇したらやろう」はNG。まず動け!
そして、「〇〇したらやろう」と考える人ほど失敗しがちであるとも述べられています(p27)。まず一歩踏み出すこと、それが成功の鍵です。
この話、私にとっては耳が痛い話でした。時間ができたら簿記の勉強をしようと考えていましたが、忙しさを理由にずっと手を付けずにいました。そのため、朝の8時から9時を簿記の勉強に充てることにしました。勉強せざるを得ない環境を作ることで、行動に移すことができました。
私が考えるに、人間は「〇〇したらやろう」という意志だけで行動できません。仕組み化により意志の介入する余地をなくすことが重要ではないかと私は考えています(この内容が本文に書かれているわけではありません)。
コンセプトが命。誰に、何を、どうやって届けるか?
ビジネスを軌道に乗せる鍵は「コンセプト設定」。
- 誰に(ターゲット)
- 何を(テーマ)
- どのように(手段)
この3つを決めることが大前提です(p47)。

テーマを定める際には、「AからBへ変わる」という方程式を使うと明確になります(p49)。顧客の問題や悩みを解決するようなサービスを提供することが、コンセプトのカギとなります。
また、「何のためにビジネスをするのか」というコア・メッセージを定めることが重要です(p56)。この根本にある理念をもっていることで、困難があっても乗り越えていける強い精神を得られるのではないかと個人的には思います。
商品はオリジナルじゃなくていい!
「100%オリジナルの商品でなくてもよい。役立つかどうかが重要」というのが著者の主張です(p81)。
商品の作り方もポイントで、以下のような要素を組み合わせてバリエーションを増やせます(p76)。
- 制作者(自分 or 他人)
- 形態(モノ or サービス)
- 販売場所
- 販売方法(自分で売る or 他人に任せる)
価格設定では「松竹梅の法則」を使うのがおすすめ(p96)。松竹梅の法則とは何なのか説明します。まず、3つの価格の異なる商品を設定します。
- 松(まつ)=最上級(高級・高価格)
- 竹(たけ)=中級(標準・中価格)
- 梅(うめ)=下級(廉価・低価格)
この三段階の選択肢を提示すると、多くの人が真ん中の「竹」=中価格帯を選ぶ傾向がある、という心理法則です。安すぎると質が心配、高すぎると損をするかもという心理が働くためです。
これをマーケティングや販売戦略に応用することで、顧客に中価格帯の商品を選んでもらいやすくなるのです。
また、高額商品を一つ用意することで、自分自身の「価値観=セルフイメージ」を広げることができるとも述べています(p102)。どういう意味かというと、自分の商品価値を低く見積もらないための対策です。
あなたが販売する商品について、1000円程度の価値があるだろうと自分で思っているとします。しかし、他者に価値を判断してもらうと、5000円、もしくは1万円の価値があるということになる可能性も十分にあります。
自分では高いと思っても、買ってくれる人はいるかもしれません。勇気を出して強気の値段設定にしてみるのはいいかもしれませんね。
なお、無料商品を先に出すと「クレクレ星人」ばかりが集まり、ビジネスがうまくいかないという警告もあります(p108)。
例外はソシャゲなどでしょうか。無課金だとキャラ育成やゲーム進行に苦戦しますが、課金することでガチャを回せる、といった甘言で課金を誘発するビジネスモデルですね。
このビジネスは、資金を潤沢に持っている企業であれば実行可能ですが、個人がやるには初期投資が足りません。
最初は無料→後から有料という戦略は、ひとりビジネスでは手を出さないのが吉です。
自分メディアを育てよ(p116)
インターネットを活用する際の基本三点セットは以下の通り(p116)。
- ホームページ
- ブログ
- メルマガ

そして、SNSやYouTubeはこれらに人を誘導するための“導線”として活用します。SNSには、ブログの一部とリンクを貼ることで誘導効果を高める工夫が必要です。
2025年7月現在、私はこのブログを開設して10記事ほど書きましたが、残念ながらなかなかPV数が伸びていません。SNSを活用して、ブログへのアクセス数を増やすことも検討したいと感じました。
集客の最強手段=「紹介」(p159、p179)
最強の集客方法は「紹介=口コミ」です(p159)。
そのためにも、ターゲットを狭めて、刺さるメッセージを作る必要があります(p179)。結果として「あの人にぴったり」と紹介されやすくなります。
お金の仕組みを整える(p206)
売上の一部をfacebook広告費用にまわし、それにより自身の商品の認知度を高め、商品の売り上げを伸ばすことが提案されています(p206)。
また、プライベートとビジネスの銀行口座・クレジットカードは必ず分けて使うことで、経理・意識の両面で効果的だと述べています。
ひとりでも仲間は必要(p236)
「ひとりビジネスは、コミュニティをつくるビジネスである」と明言されています(p236)。
具体的には、自分以外のスペシャリスト8人を集め、ゆるやかなチームを結成することで、人生の支えとなる人間関係を構築できると述べられていました。

これについては、少し行動に移しにくいのではないかと感じました。
職場の人間関係に悩んでフリーランスを目指す人は少なくありません。もしその理由が「人と関わりたくない」「組織に疲れた」というものであれば、フリーランスになってからチームを作りたいとは思えないのではないでしょうか。
人間関係から逃れるために独立したのに、また誰かと協力することに抵抗を感じてしまう――そうなると、チームでの仕事や共同プロジェクトに踏み出すハードルは意外と高いものです。
「なぜそれをやるのか?」を問い続ける
最後に重要なのは、「Why(なぜやるのか?)」という問いを忘れないことです。
迷ったときやブレを感じたときは、自分の「ミッション」と「ビジョン」を見つめ直す時間をとることが大切です。
勉強などでも、この考えは非常に大切だと思います。「なぜこの勉強をする必要があるのか」を明確化しておくことで、勉強へのモチベーションは高まるでしょう。
まとめ
『ひとりビジネスの教科書』は、実践的なノウハウに加え、「一歩踏み出す勇気」を与えてくれる一冊です。
特に印象に残ったのは以下の点です。
- 「〇〇したらやろう」と考えるのはやめて、今すぐ始める(p27)
- 「誰に×何を×どうやって」のビジネス構造を明確にする(p47)
- 無料ではなく、有料の商品を最初に出す(p108)
- 紹介による集客がもっとも強い(p159)
- 自分だけのビジネスではなく、信頼できる仲間を持つ(p236)
ひとりで稼ぐ時代にこそ、読む価値のある一冊です。
Amazonプライム無料体験の新規登録※この記事は『ひとりビジネスの教科書』(著:佐藤伝/発行:学研プラス)に基づいて執筆しています。
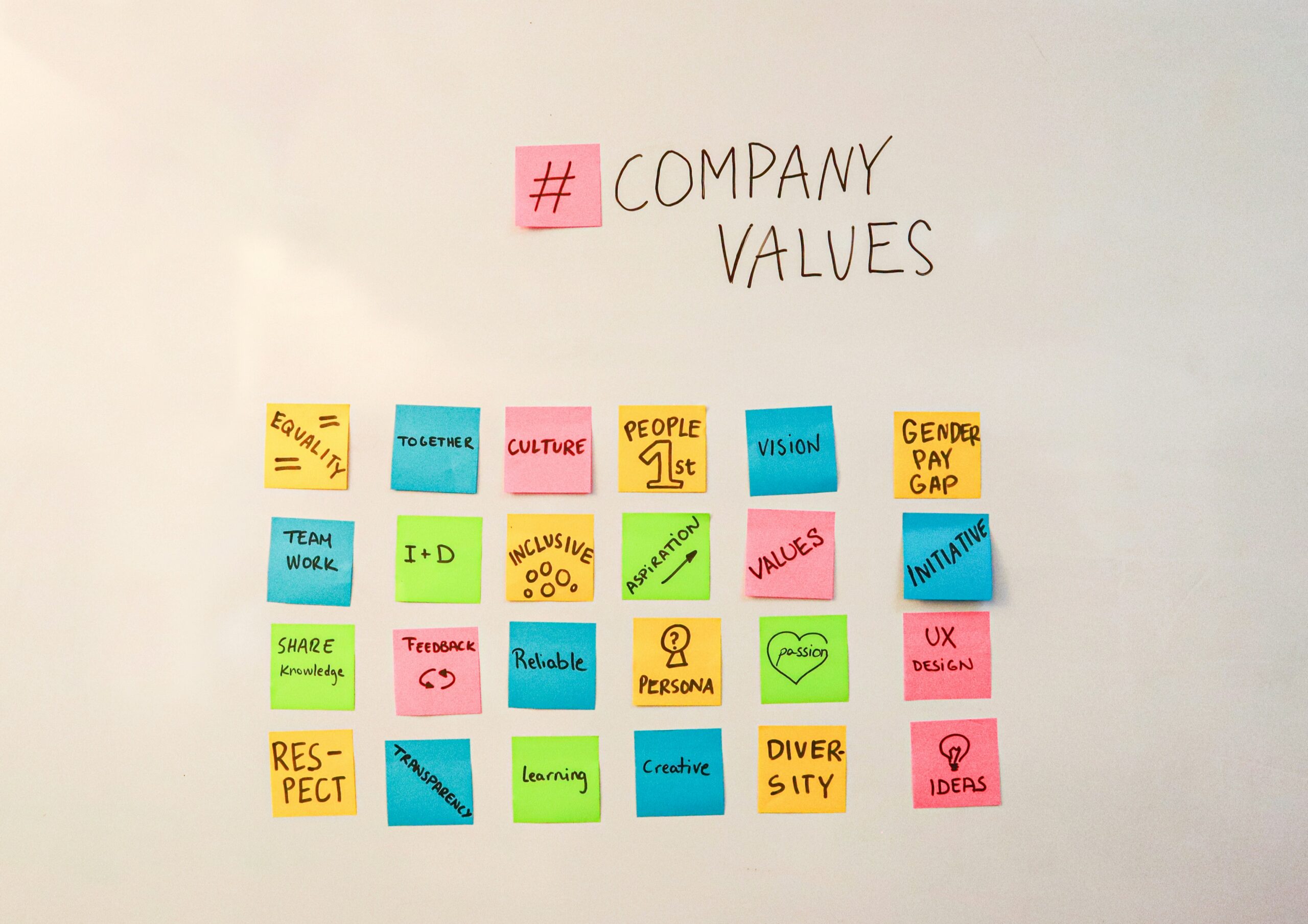


コメント