※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
この本を読んでほしい人
・今後のキャリアに不安を感じている人
・「人生100年時代」にどのように働き、生きるかを考えたい人
・FIREやセカンドキャリアに興味がある人
・これからの社会の変化に備え、自分に必要なスキルを考えたい人
本の内容
技術は進化しているが、社会の仕組みは追いついていない
本書の冒頭で強調されているのが、「技術的発明は進歩しているが、社会的発明(制度や仕組み)は遅れている」という事実です。
AIや自動化技術は急速に進化していますが、私たちの働き方、教育制度、老後の過ごし方などは、まだ旧来の枠組みにとらわれています。長寿社会に突入している今、このギャップを埋めるためには、自分自身が変化に対応し、行動する力が問われているのだと感じました。

“好奇心”が未来の武器になる
変化の時代に求められるのは、単なるスキルだけではありません。著者が挙げる、機械に代替されにくい分野である、「コミュニケーション」「思いやり」「マネジメント」「創造性」などは、まさに人間ならではの強みです。こうした力は、好奇心から育まれるといいます。
確かに、日々の仕事でも「なんでだろう?」という疑問から、意外なアイデアが生まれたり、チームとの関係性が良くなったりする場面があります。好奇心を育てることは、創造的な生き方の土台になっていくと実感しました。
早期の自己投資は長期的なリターンにつながる
人生が長くなるということは、「自己投資のリターン期間が長くなる」ということでもあります。若いうちから学びや経験に投資すれば、その恩恵をより長く受け取れるのです。
私自身、「どうせ今やっても…」と先延ばししてしまうことがありますが、この視点はハッとさせられました。やるなら早い方がいい。特に、これからのキャリアを見据えると、意識的なスキル獲得がカギになりそうです。
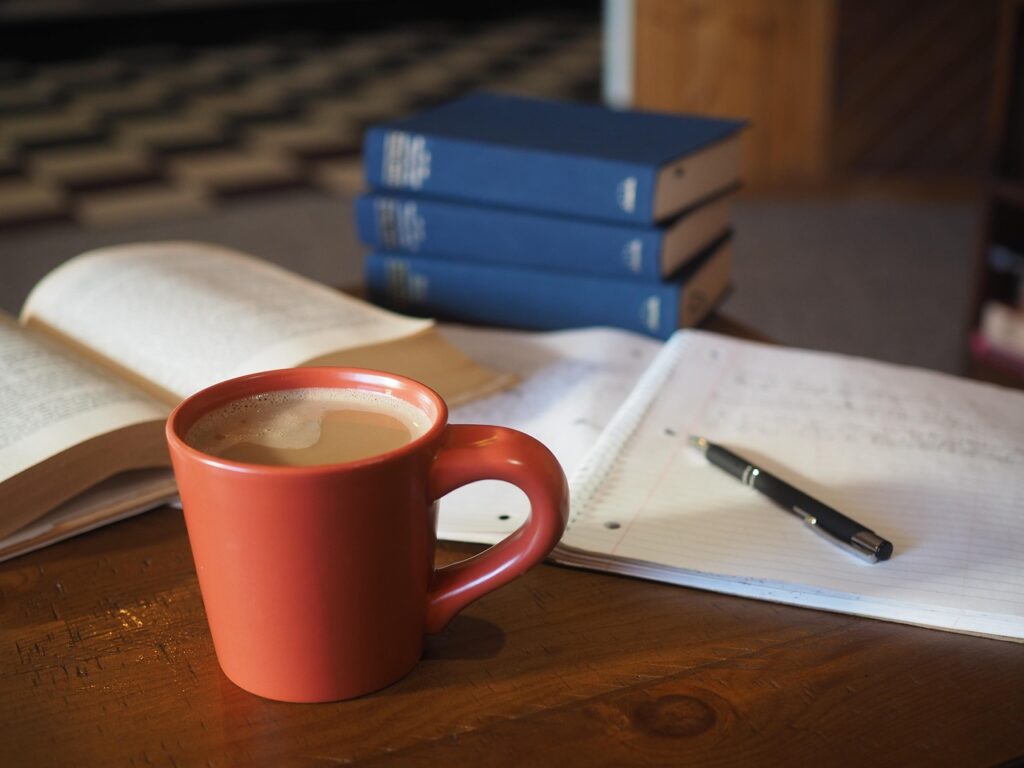
「トンネリング」から抜け出すには
本書では、「トンネリング」という心理状態も紹介されています。これは、時間やお金といった資源が不足しているときに、人は視野が狭まり、目の前のことしか考えられなくなる現象です。
例えば、仕事が立て込んでいるときに、「とりあえず目の前のメールを返す」「やるべき優先順位を考える暇がない」という状態になりがちです。その結果、重要だけど緊急でないタスクがどんどん後回しにされてしまいます。気が付けば重要な仕事の締め切りが近づいているのに、ほとんど手を付けられていないという事態になりかねません。
このような状態を抜け出すには、「未来の自分」にとって意味のある行動を優先することが大切だと著者は述べています。まさに、時間の切り売りではなく、未来への投資が求められているのです。
引退のタイミングが寿命を左右する?
驚いたのは、引退年齢と寿命の関係に関するデータです。労働を引退する年齢が遅い人ほど、長生きする傾向があるそうです。FIRE(早期リタイア)を目指す人にとっては、少し耳の痛い話かもしれません。
私自身もFIREに憧れていますが、「完全に社会から離れることは逆効果なのかも?」と考え直すきっかけになりました。少しでも社会とつながり続ける働き方の方が、健康にもよさそうです。

キャリアは“流動的”にデザインする時代
かつてのように「ひとつの会社で定年まで働く」時代ではなくなりました。いまやキャリアは流動的で、複数のステージを経ながら柔軟に生きていく時代です。だからこそ、「今の仕事が未来につながるか?」という視点を持つことが重要だと感じます。著者は、学びながら働く「学習するキャリア」が求められると述べており、これは非常に納得感がありました。
会社で仕事をしても自身の能力が向上していない場合、それは単なる時間の切り売りです。アルバイトと変わりません。今お金をもらえているからよいという考えではなく、将来に役立つスキル・能力を仕事で身につけようという気持ちで仕事に取り組むべきだと感じました。
「未来の自分」を描くために
本書は、「将来どうなりたいか」「そのために何をするか」を考える重要性を繰り返し説いています。特に心に残ったのは、「今の行動が未来を決定する」という“再帰性”と、「時間配分を自分で変えられる」という“可変性”です。この2つの考え方を持つことで、「なんとなく毎日を過ごす」ことから抜け出せる気がしました。
多様な人と関わる、社会を見渡す
これからの時代を生き抜くために、著者は「多様な年齢層が混ざるコミュニティ」への参加や、「社会を俯瞰して見る習慣」の大切さも提案しています。変化の兆しに気づくには、日常の外に目を向けることが不可欠です。身近なところでいえば、異業種の人と話すことや、新しいイベントに顔を出してみることも大切だと感じました。

「ステレオタイプ」から自由になる
私たちは、「大学→就職(終身雇用)→定年→老後」というモデルにどこか安心感を持っていますが、それがもはや機能しなくなっているのは明らかです。『ライフシフト2』は、そうした“常識”を手放し、「自分なりのライフプラン」を描くことの大切さを教えてくれます。
そして、必要なのは技術的スキルだけではありません。人間関係を築く力、マネジメント力、リーダーシップ。こうした“人間らしい力”が、これからの長い人生を豊かにしてくれるはずです。
まとめ
『LIFE SHIFT2』は、「未来は予測できないが、準備はできる」という強いメッセージを投げかけてくれる一冊です。不確実性の高い時代において、「どうありたいか」という“ありうる自分像”を描くこと。そして、その実現のために今から行動を起こすこと。これが、これからの人生に必要な姿勢だと感じました。
長く働き、学び、関わり続ける人生を設計するには、「変化を受け入れる力」と「自分で選択する意志」が不可欠です。本書はそのためのヒントが詰まった、現代人の必読書です。未来に悩むすべての人に、心からおすすめします。
※記事内容は『LIFE SHIFT2: 100年時代の行動戦略』(著:アンドリュー・スコット、リンダ・グラットン/東洋経済新報社)に基づいて執筆しています。



コメント