※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
最近、上司が私の発言をことごとく否定してくるような状況が続き、心身ともに疲弊していました。
朝起きるのもつらく、ベッドから出られない日も。
「これは自分の努力不足なのか、それとも何かのサインなのか?」そんな疑問を抱いていたときに、この本に出会いました。
この記事では、その本の内容を自分なりにまとめて紹介します。
ただし、私は医療従事者ではありません。記載する内容はあくまで一般読者の立場からの要約であり、情報は参考程度にとどめてください。
私がこの本を手に取った理由
朝起きるのがつらいという症状は、適応障害にみられる症状のひとつであるとネット記事で見ました。
適応障害とは何なのか、そしてどのようにすれば治療できるのかを調べたくて図書館に足を運んだところ、この本に出合いました。
ページ数は96ページと少なく、気軽に読めます。メモをする時間含めて1時間ほどで読み終わりました。
短時間で適応障害に関する基本知識や、その改善方法について学ぶことができました。
この本を読んでほしい人
心の不調といえば「うつ病」がよく知られていますが、「適応障害」という言葉はあまり聞きなじみがない方も多いのではないでしょうか。
でも本書を読むと、実は「自分もこれに当てはまるかもしれない」と感じる人も多いのではと思います。
「最近、心がつらいけど、それをうまく説明できない」
「こんなことで悩んでいるのは自分だけなんじゃないか」
そう感じている方にこそ、この本を手に取ってみてほしいと思いました。
本の内容
本書の表紙には、「心の病の中では軽い不調と思われがちだが、長年苦しむ人も多い」とあります。
「適応障害」は決して侮れない病気であり、正しく理解し、対応することが必要だと強く感じました。
適応障害とは何か?
適応障害は、「特定のストレス因子へのとらわれ」と「そのストレスへの対処技能(コーピングスキル)の不足」が原因で起こるとされています(p2)。
症状としては、憂鬱、不安、反社会的行動、意欲の低下、自律神経症状(頭痛・食欲不振・不眠など)が見られます(p10)。

適応障害とうつの違い
適応障害とうつの大きな違いは、ストレス因から離れたときに抑うつ状態が緩和されるかどうかです。
適応障害では、特定のストレス因や環境から離れたときは症状が緩和する傾向にあります。
一方で、うつは特定のストレス因や環境から離れても抑うつ状態が続く傾向にあります。
「頑張りすぎてしまう人」ほど神経伝達物質の働きが阻害され、うつに至るケースもあり(p15)、「過剰適応」とも言われています。
私自身、最近の体に出ている症状が、大学院の修士論文前の時期に経験した症状と似ているなと感じ、自分の弱点や傾向を見つめ直すきっかけにもなりました。
どのくらいで治るのか?
3〜4割の人は半年以上症状が続くそうですが、早ければ1〜2ヶ月で回復する人もいます(p40)。
まず大切なのは、自分にとって何がストレス因子なのかを明確にすることです。
治療方法について
治療としては、認知行動療法、問題解決療法、行動療法などが紹介されています(p47)。
認知行動療法は、考え方のクセに気づいて修正する方法ですが、時間がかかる上、エビデンスもまだ弱いそうです。
一方、問題解決療法は「問題を定義し、解決策を立てて実行する」という流れで、社会復帰のスピードが統計的に早いというデータもあるとのことです。
問題解決力を高めるレッスン
Part3の章では、次のような具体的なステップが紹介されていました(p52〜)。
- ストレスを感じた出来事に対し、どんな認知・感情・身体反応・行動があったかを振り返る
- 理想と現実のギャップから問題を定義(p61)
- 問題を細かく切り分けて、扱いやすくする(p63)
- SMARTゴールを設定する(p64)
- 解決策についてPros/Cons分析を行い、実行する(p72)
- 行動計画を立てて実施し、達成度とその影響を振り返る
SMARTゴール
SMARTゴールとは、目標を達成しやすくするための考え方で、「具体的」「測定可能」「達成可能」「関連性」「期限がある」の5つの要素を満たすように目標を立てる方法です。
例えば、適応障害克服のためのSMARTゴールを立てるとすると、以下のようになります。
「3ヶ月以内に、毎日30分の散歩を週5回行い、気分の変化を日記に記録することで、ストレス軽減を目指す」
5つの要素を意識して目標を立てると、何から始めればいいかが明確になり、無理なく着実に進めることができると言われています。
Pros/Cons分析
Pros/Cons分析とは、何かを決めるときに「その選択をした場合の良い点(Pros)」と「悪い点(Cons)」を整理して比較する方法です。
メリットとデメリットを比較して、メリットのほうが多ければそれを実行すべきであると冷静に判断できます。
逆に、なかなか行動に踏み出せないときに、失敗したときのデメリットを考えてみると、意外とデメリットが少ないことに気付けるでしょう。
選択や行動に悩んでいる場合は、ぜひPros/Cons分析を実施してみてください。
周囲のサポートも大切
家族や友人から「つらかったね」と共感してもらえるだけで、心が少し休まる——本書で紹介されたこの言葉に深く共感しました(p90)。
私も、家族や友人に相談して、心が休まりました。現状が変わらないにしても、誰かに話せたことで心にゆとりが持てます。
誰かに理解されることの大切さを、改めて実感しました。

まとめ
適応障害は、「特定のストレスへの対応が難しい」ときに誰にでも起こりうる病気です。
自分が悪い、自分が弱い——そんなふうに思い詰めてしまう前に、まずは「適応障害」という視点を持つことで、状況を客観的に見つめ直すことができるかもしれません。
「最近なんだかしんどい」
そう感じている方にこそ、この本を読んでみてほしいです。
無理せず、ひとつずつ、自分を知っていくヒントがこの本には詰まっていました。
※この記事は『「適応障害」ってどんな病気?』(著:浅井逸郎/出版:大和出版)に基づいて執筆しています。
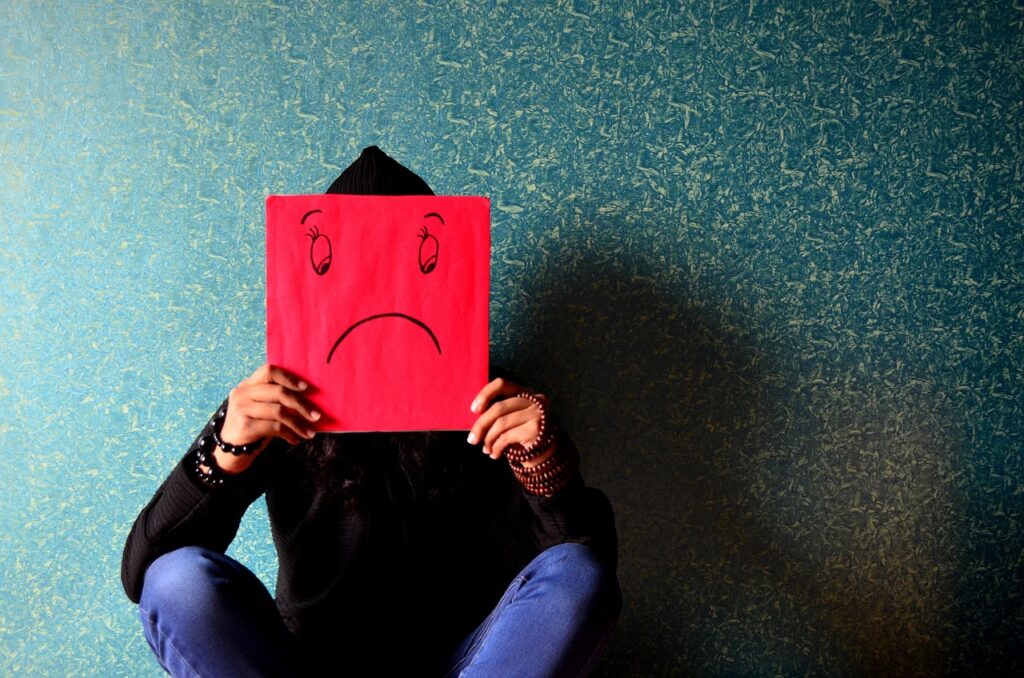


コメント